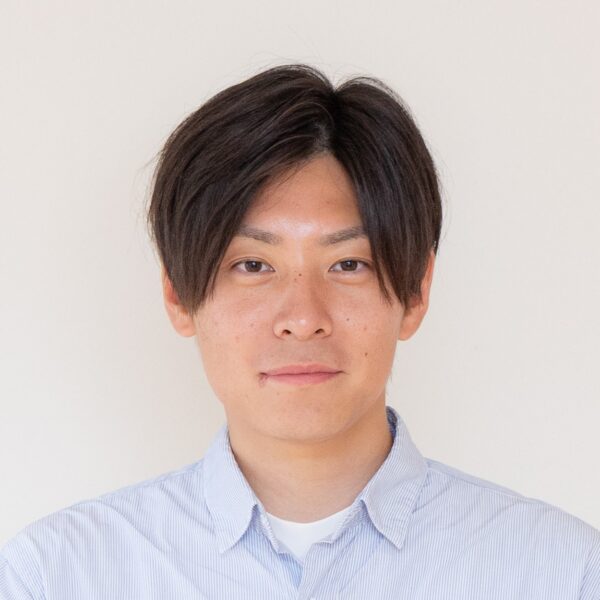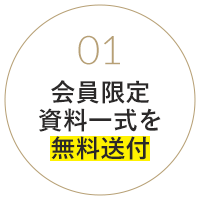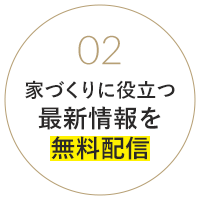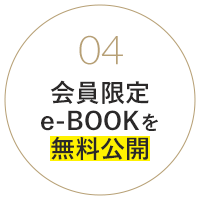シリーズでお送りしてきた社員旅行レポートも今回で最終回。
最終日のレポートをまとめていきます!
東大寺
最終日は東大寺からスタートです。
3日目の宿泊先である奈良ホテルから徒歩17分。歩きながらすれ違う鹿は、何匹見ても飽きないですね。
ついつい写真を何枚も撮ってしましました。
東大寺は、中学時代の修学旅行で見学したことがあり、実に13年ぶりとなる訪問でした。
2回目とはいえ、やはり見る目が変わると見応えがあり圧巻の迫力でした。
正門(南大門)
境内に入るとまず最初の現れるのは正門の南大門。
創建時の門は平安時代に大風によって倒れ、現在の門は鎌倉時代に再建されたものです。 

入母屋造の五間三戸二重門で、下層は天井がなく腰屋根構造となっています。
屋根裏まで達する円柱は18本あり、長さは19mにも及び、門の高さは25mもあるとのこと。
そしてこの南大門の中には“東大寺の仁王さん”こと金剛力士像が安置されています。
昭和63年から平成5年までの5年間で修理されたとはいえ、820年前から南大門を守り続ける守護神は鋭い目つきと力強く筋肉質な体つきですが、衣のひだといった細部の表現はとても繊細で、日本における最大級で傑作の木造彫刻です。



大仏殿(金殿)
その先へ進むと、誰もが一度は教科書で見たことがあるだろう、“奈良の大仏”が鎮座する大仏殿(金殿)があります。
奈良時代に創建されたものの、二度の兵火に遭い現在は江戸時代に再建されたもの。
中には、各時代の大仏殿の模型が展示されており、鎌倉時代の大仏殿に関しては桁行11間もあったとのこと。
大仏様は何度見ても、その大きさと存在感に圧倒されます。




二月堂・法華堂(三月堂)
二月堂は、清水寺のような懸造りで、ル・コルビュジエのラ・トゥーレット修道院を彷彿させます。
石段を上ると、舞台からは奈良市内や周辺の山が一望できました。
二日目の室生寺や、三日目の三輪山といい、とにかく旅行中は足を鍛えられます(笑)。



法華堂(三月堂)は東大寺の中でも現存する最古の建物で、非常に見応えがあります。
法華堂は正堂(奈良時代の原型部分)と礼堂(鎌倉時代の増築部分)の二つの部分から成っており、建物の左右で建築様式の違いが一目で分かるのが最大の特徴です。
木材や屋根の風化具合、柱の太さなどに注目すると、時代の差を実感できます。

正堂と礼堂の接続部にあたる「造り合い」
などなど、東大寺だけでも見どころが満載です。
新薬師寺
昼食に美味しい蕎麦を食べた後(写真撮り忘れた・・・)、新薬師寺へ向かいました。
新薬師寺は薬師寺とは宗派が異なるため、NEW薬師寺という意味ではなく「霊験あらたか」な薬師寺という意味だそうです。
外観は、勾配の緩い軽快な屋根と、シンプルで落ち着いた気品が漂う雰囲気です。
垂木は上下二段あり、下部は丸型で上部は角型となっており、中国から伝来した建築様式とのこと。
同じ時代に創建された法華堂(三月堂)では我が国独特の形式で、上部・下部ともに角型となっております。


最後に
2025年オガスタ社員旅行を総括すると、「建築」と「旅」をふんだんに堪能した「人生の宝物」になるかけがえのない4日間でした。
私自身、オガスタでは初めての社員旅行でしたが、今年は過去と比較しても特に内容が盛りだくさんだったとみんな口を揃えます。
初日は車での移動時間が長かったものの、2日目以降は1日平均2万歩以上歩きました。
車や交通機関を利用することが当たり前の日常だからこそ、歩くことの楽しさや人間らしさというものを改めて実感しました。
建築巡りだけでなく、昼食や夕食にはみんなで美味しいものを食べたり飲んだりして、普段の仕事中では取れないような深いコミュニケーションの時間もあります。
「建築」、「歩」、「食」。
そして日本建築とはどこから来てどのように解釈され、そして現代まで継承されてどのように変化してきたのか。
忙しない日常の中では、あまり考えることができないことを考えるきっかけとなる、素晴らしい研修旅行でした。