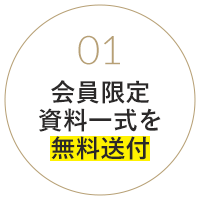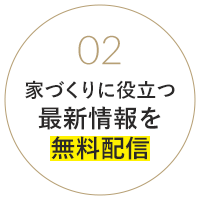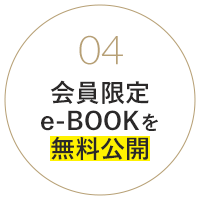新しい農家住宅のかたち「乙の家」
設計:一級建築士事務所 ma ヤマシタマコト 監督:小林 秀昭 大工:佐久間建築
- コンセプト
- 胎内市の乙(きのと)は小さな集落だがその歴史は長く、古くから信仰の中心地として知られてきた。
そもそも「乙」という地名は、天平8年(736年)に聖武天皇の勅願により開山した「乙寺(きのとでら)」に由来する。
この寺には釈迦の左眼舎利が安置されているという。
平安時代になると後白河天皇から金塔を寄進された際に「宝」の一文字が加えられ、「乙宝寺(おっぽうじ)」と改名され、現在でも多くの参拝者が訪れる。
とはいえ普段はいたって静かな地域で、通り沿いには古い農家住宅が軒を並べている。
切り妻の瓦屋根に杉の下見板張りの外壁が目立つ。どの家も敷地が広く、蔵を備えた家も少なくない。
本計画も同様な古く大きな農家住宅の建て替えである。
かつては旅館業も営んだこともあるというその家はいかにも立派であったが、老朽化が進み、また寒く、建て替えることになった。
この地に新しく建て替えられる家のあり方とはどういうものか、また二世帯住宅ということもあり、二つの家族が適度な距離を持ちながら暮らしていくあり方はどういうものか、ということがテーマとなった。
- 外観
- 地域の農家住宅に倣い、杉板の下見板張りのシンプルな箱型にすっきりとした切り妻屋根を架けた。
下見板の押縁(ささらご)は455mmピッチで付けられているものが多く見られるが、ここでは南面にのみ、それも約一間ピッチとし、押縁の見つけも30mmとあえて太くした。
前面道路側は西面となるので開口部を抑えたいところだが、表情も欲しい。そこで縦長の開口として、縦ルーバーをつけて西陽を防ぐとともにアクセントとした。
- 内観
- 一階は親世帯、二階は子世帯で、玄関ホールだけを共有する。
一階は天井の高さを抑えて栂の小巾板としている。縁側はいらない、とのことだったので、1800mmの高さの窓を床から300mm上げて取り付けた。このことにより、三間幅の大開口ながらも落ち着きのある空間になったと思う。
農作業小屋のある東側には収納を備えた勝手口を設け、水廻りに直行できる配置となっている。
二階は勾配天井で開放感・躍動感のある空間とした。天井は一階と同様に栂小巾板で仕上げ、間接照明で照らす。
横長の窓からは隣家の庭を望むことができる。
上下階をつなぐ階段はストリップ階段として、縦長の窓からの光を取り込んで明るいホールとなっている。
- 空調計画
- 二世帯であり、また気積が大きいために個々で空調のコントロールができるよう、上下階に冷暖房のためのエアコンを用意しているが、暖房については基本的には一階の床下暖房のみで運用できるように計画している。吹き抜けがないため、建物全体の空気循環を促進するためのアローファンを上下階を貫通するように設けている。
- 規模・性能
- ■ 敷地面積 135.76坪(448.70㎡)
■ 延床面積 58.33坪(192.36㎡)
■ Ua値:0.27 W/㎡K
■ Q値 :0.77 W/㎡K
■ C値 :0.3㎠/㎡
■ 太陽光パネル 7.74kw
■ 長期優良住宅認定
■ 耐震等級3
■ 木造在来工法 二階建て
- ひとこと
- この現場では若いふたりの大工さんが始まりから終わりまで大活躍してくれました。
大変頼もしく、ありがたくさえありました。
大工さんが楽しくものづくりができる、そして稼ぐことができる現場がもっと増えますように、と願います。